脱炭素のすゝめ(4) 脱炭素対応が競争力に
2022/11/14
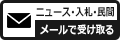
|
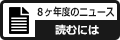
|
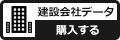
|
いいね | ツイート |
| 0 |
ゼロボード代表取締役 渡慶次道隆
自社が施工する工事現場で、どれだけの二酸化炭素が排出されているのか―こんな疑問に向き合う建設企業は、まだ少ないだろう。しかし、事業に伴う二酸化炭素排出量の算定・削減を求める金融市場からの圧力は、確実に強まっている。経済産業省の排出量可視化に関する検討会で委員を務める渡慶次道隆氏は「難題だからこそ、データを出せる企業の価値が高まる」と説く。品質や価格だけでなく、脱炭素への対応が建設業の競争力に直結する日はそう遠くない。
ビジネスのルールが大きく変わろうとしている。発端は「気候関連財務情報開示タスクフォース」(TCFD)が2017年にまとめた、企業に排出量の自主開示を求める報告書だ。国際的な開示義務化の流れを受けて、国内でも東京証券取引所が、最上位のプライム市場に上場している企業に開示を求めている。
非上場の地域建設業にとっても他人事ではない。TCFDに準拠すると、自社の事業活動に加えて、他社との取引による排出量も開示しなくてはならない。こうした企業が施主となれば、受注した建設企業も建設工事や、竣工後の建物の運用でどれだけ二酸化炭素が排出されるかを算定し、そして削減することを求められるようになる。
製造業と異なり、「一品受注生産」の建設業は、現場ごとに二酸化炭素排出量を算定しなくてはならない。重層下請けの産業構造の中で、下請けの作業内容や資機材を把握し、積算のように排出量を積み上げていく必要がある。「いずれは、目標排出量を定めるような工事契約も出てくるのでは」(渡慶次氏)
こうした潮流を捉え、渡慶次氏が代表取締役を務めるゼロボードは、建設業に特化した排出量算定サービスの開発をゼネコンと連携して進めている。設計段階では想定している部材や作業内容から推定し、施工段階では日報などから実際の排出量を算出。目指すのは、日次単位で排出量を管理し、施工管理にフィードバックできる体制だ。
ゼロボードは今年、横浜銀行などと連携して地元の工藤建設に排出量算定サービスを試行導入。他にも多くの金融機関から問い合わせがあるという。これは、TCFDに基づくと、銀行も融資先の排出量削減が求められるためだ。脱炭素への取り組みに対して金利を優遇するローンも続々と登場した。
政府内では、炭素税の導入に向けた政府の議論も本格化。排出量の算定・削減は企業の資金繰りにも影響するファクターになりつつある。
受発注や資金繰りなどあらゆる場面で強まる排出量削減の声を、圧力と取るかニーズと取るかは受け手次第だ。渡慶次氏は言う。「この声に応えられるゼネコンが評価されるようになる。変化は、意外なほど早く来るはずだ」
| この年の国土交通省の発注予定案件 | この年の国土交通省予算情報 |
国土交通省の公共事業ニュース
国土交通省の行政・建設経済ニュース
国土交通省の民間事業ニュース
|
国土交通省の入札公示情報
国土交通省の入札結果情報
|
特集コーナー
このコーナーでは、入札情報関連の話題や建設業界注目の情報、工事ニュースなどを取り上げます。


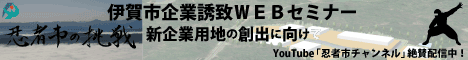






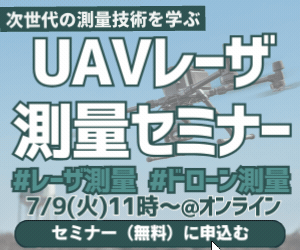
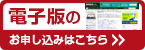
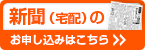


![<font color="#ff0000;"><b>[New]</b></font>川崎市まちづくり局特別企画 - 未来をつくる市内の建築物](/feature/kikaku/24/image/pl240305000001_s.jpg)
![<font color="#ff0000;"><b>[New]</b></font>Catch-up](/feature/kikaku/22/image/pl220622000002_s.jpg)







