群馬県建設業協会は、ICT活用工事(土工)の全工程を学ぶことができる「ICT土工研修」を2017年度から開催している。この取り組みは、生産性向上にも必要な技術・技能の学びを促す、国土交通省の「中小・中堅建設企業等の建設リカレント教育等支援事業」でモデル事業にも選定されている。地域単位での技術者育成に注力する青柳剛会長に、技術者の生涯教育のあるべき姿を聞いた。
ホーム > 特集 > 特集 > 人材育成は未来への投資(第4回)
(2019/03/27)
人材育成は未来への投資(第4回)

―計画的な研修の重要性を説かれています。
「地方の建設業は、公共工事の事業量の増減に応じて年度ごとの仕事を組み立ててきた。しかし、人材育成は複数年度にまたがる計画的な取り組みだ。人口減少による人材不足が深刻化している今、場当たり的な人材育成から脱却しなければいけない。景気が悪いときも社員を育て、未来に投資するという経営者の覚悟が問われる」
「学生を採用しようとするとき、研修メニューをきちんと提示できないと、就職先に選んでもらうのは難しい。また、研修の実効性が乏しければ、たとえ就職しても定着してくれない。将来どんな技術者になれるか、というキャリアパスを示すことは極めて重要だ」
―地域単位での技術者育成に力を入れる狙いを聞かせてください。
「個々の企業にできることには限界がある。社員を群馬県から東京都に送り出して研修を受けさせるには、建設企業に一定程度の余力が要る。そこで講師を群馬県に呼び、計画的な研修を提供できるようにしたいと考えた。個社では難しくとも、協会を通じてコストとリスクを分散すれば実現できる。群馬県内のどこからでも1時間ほどで来られる群馬建設会館を学びの拠点として、多忙な技術者も無理なく研修を受けられる環境を整えていく」
―技術者の生涯教育をどのように進めればよいとお考えですか。
「研修は、先輩の背中から学ぶ『O-JT』と、計画的な研修の『Off-JT』、習得した技術に対する『評価』の3角形で成立する。従来の建設業の技術者育成はO-JTに偏り過ぎていたのではないか。ICT活用工事をはじめ、新しい技術は先輩の背中を見ているだけでは身につかない。技術者としての原理原則を学んでほしいし、コミュニケーション能力も身につけてほしい」
「その一方で、キャリアに応じた研修内容を提供することも重要だ。17年、18年に行ったICT土工研修は、入職から3〜5年目を対象とした。今後は10年生くらいを対象に、工期とお金、工程管理をメインに据えた研修を提供することも考えている」
「研修して、それで終わりにしてはいけない。『フォローアップ研修』を開き、学んだことを企業内でどのように水平展開しているかをヒアリングしている。また、複数社に跨がる研修を開けば、技術者どうしの横の連携を促すこともできる。優れた技術を互いに学び合うことで、一層のレベルアップが期待できる」
―建設系CPDなどの継続学習の仕組みは、技術者教育にとってどのような意味を持つとお考えでしょうか。
「学びの蓄積を第三者的に評価する仕組みは、技術者の大きな励みとなるのではないか。技術者のステップアップを補助するツールの一つとも言える。ただ、技術の研さんは、自身の血肉となったかどうかが最終的な評価。それに資するような研修を提供していかなければならない、とも考えている」
その他の特集
 建設資材価格マーケット(2024年3月)
建設資材価格マーケット(2024年3月) 
- [New]川崎市まちづくり局特別企画 - 未来をつくる市内の建築物

- [New]Catch-up

- 建通新聞購読料のお支払いに『口座振替』が使えます!

 建設資材価格マーケット(2024年2月)
建設資材価格マーケット(2024年2月) 
 建設資材価格マーケット(2024年1月)
建設資材価格マーケット(2024年1月) 
- 全国の企業・就活生応援 建設業界に熱視線!

 建設資材価格マーケット(2023年12月)
建設資材価格マーケット(2023年12月) 
 建設資材価格マーケット(2023年11月)
建設資材価格マーケット(2023年11月) 
- 連載「脱炭素のホンネ」

 建設資材価格マーケット(2023年10月)
建設資材価格マーケット(2023年10月) 
- Catch-up<2023年10月〜11月号>

 建設資材価格マーケット(2023年9月)
建設資材価格マーケット(2023年9月) 
 建設資材価格マーケット(2023年8月)
建設資材価格マーケット(2023年8月) 
- Catch-up<2023年8月〜9月号>

 建設資材価格マーケット(2023年7月)
建設資材価格マーケット(2023年7月) 
 建設資材価格マーケット(2023年6月)
建設資材価格マーケット(2023年6月) 
特集コーナー
このコーナーでは、入札情報関連の話題や建設業界注目の情報、工事ニュースなどを取り上げます。
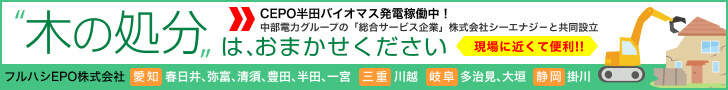
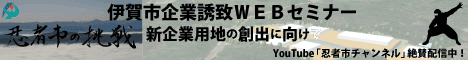




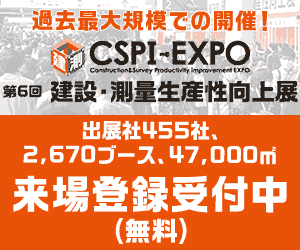
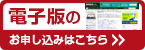
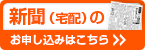


![<font color="#ff0000;"><b>[New]</b></font>Catch-up](/feature/kikaku/22/image/pl220622000002_s.jpg)






